無宗教葬儀とは?
日本の葬儀は約8割が仏式で執り行われているため、”葬儀といえば仏式”というイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?
しかし、ここ最近では、自由な形式で行なわれる「無宗教葬儀」を選ぶ人も徐々に増えてきており、葬儀の多様化が進んでいます。 一方、無宗教葬儀はまだまだ一般的とは言えないため、どのように葬儀を執り行えばいいのか分からない方もいらっしゃると思います。 そこでこの記事では、無宗教葬儀の特徴や注意点などについて解説していきます。

目 次
- ■ 無宗教葬儀とは
- ■ 無宗教葬儀の流れ
- ■
葬儀後のお骨の供養方法
- ・ 公営の墓地を探す
- ・ 永代供養をする
- ・ 宗教を問わない墓地を探す
- ・ 海洋散骨をする
- ■ 無宗教葬儀の費用
- ■ 無宗教葬儀の注意点
無宗教葬儀とは
今まで日本では仏式での葬儀が一般的でしたが、ライフスタイルや宗教観の変化に伴い、無宗教葬儀を選ぶ人が徐々に増えてきています。
無宗教葬儀は、決められた形式や儀礼に縛られることがないため、故人の遺志や遺族の想いに沿った形で故人を見送ることができます。
仏式の葬儀と無宗教葬儀との違い
無宗教葬儀は、宗教的な儀式の枠組みにとらわれないため、仏式の葬儀のような宗教的な儀式は行なわれません。
無宗教葬儀の流れ
2.黙祷:お経の代わりに全員で黙祷をします。
3.故人の経歴紹介:故人の経歴の紹介をします。
4.献奏:故人が好きだった曲を流したり、生演奏します。
5.弔電の紹介:届いた弔電を読み上げます。
6.感謝の言葉:遺族の代表者が参列者に向けて感謝の言葉を伝えます。
7.献花:遺族、親族、参列者の順に花を供えます。
8.メモリアルビデオやスライド上映:生前の映像や写真を見て故人との思い出を振り返ります。
9.お別れの儀:故人とのお別れをします。
10.閉式の辞:司会者が閉式を告げると、葬儀が終わります。
11.出棺:葬儀後は出棺し、火葬場へ向かいます。
12.会食:火葬の後に会食を行うケースもあります。
葬儀後のお骨の供養方法
公営の墓地を探す
なるべく予算を抑えて墓地を購入したい場合は、公営の墓地を探すことをオススメします。
公営の墓地には指定の宗教・宗派がなく、無宗教葬儀を行った方でも問題なく納骨することが可能なため、葬儀後の流れも比較的スムーズと言えます。
場所によって設備の内容は異なるため、いくつか候補を挙げて見比べてみましょう。
永代供養をする
永代供養とは、永代供養墓がある寺院・霊園などが、ご遺族に代わって故人のご遺骨を管理する供養方法で、宗旨・宗派を問わず、お墓を建てる必要もないため、一般的なお墓での供養に比べて費用を抑えることが可能です。
また、お墓の管理を任せることができるので、お墓の後継人がいないという方には最適と言えます。
宗教を問わない墓地を探す
一般的に、全てのお寺は宗派が決まっているといったイメージがありますが、宗教を問わないお寺の墓苑や霊園も各地に存在します。
無宗教葬を行った場合は、こういった宗派とは関係のない墓地を選んで納骨することがオススメです。
なぜなら、菩提寺が宗派を厳格に守るお寺だった場合、宗派に則った葬儀をあげていないと納骨を拒むことが多いからです。
海洋散骨をする
古来から「人は亡くなるとお墓に入るもの」というのが常識でしたが、現在では供養の形も様変わりしています。
最近では自然への埋葬を希望する人が増えてきていて、海へ散骨して自然に還るといった海洋散骨という方法も広まってきました。
お墓への埋葬と比較すると維持費がかからず、宗教などにとらわれることがないといったメリットがあります。
一般的に納骨は四十九日法要の時期に行いますが、無宗教葬儀の場合は特に行う必要はありません。
もし別の方法で行いたい場合は、「追悼式」や「記念式」という形をとることも可能です。
無宗教葬儀の費用
無宗教葬儀だけに限らず、どのような葬儀でもかかる費用としては、ご遺体の搬送や葬儀・火葬に必要な費用、会葬者の飲食接待費などが挙げられます。
また、無宗教葬儀の一種である火葬のみを行う直葬の場合は、一般的な相場として10〜30万円程度かかります。
そのため、上記の金額に合わせて、実施したい内容に応じた追加料金がかかると考えておけばよいでしょう。
無宗教葬儀の注意点
菩提寺がある場合は無宗教葬儀を行うことができない
無宗教葬儀を行った際の遺骨は、宗教宗派を問わない公営墓地や民営墓地に納めなくてはなりません。
そのため、菩提寺(檀家のお寺)を持っている方は、基本的には仏式の葬儀を行う必要があります。
菩提寺のお墓は、その宗教宗派の檀家のものであるため、無宗教葬儀の場合納骨を断られてしまう可能性もあるため十分注意しましょう。
無宗教葬儀ができる方は、一般的に菩提寺がない方が対象となります。
内容のプランニングをしっかり行う
自由な内容の無宗教葬儀は、決められたものが特にないため内容がしっかりしていないと、あっという間に終わってしまいます。
そのため、内容をしっかりプランニングしていないと、後々まで悔いが残ってしまう可能性もあります。
また、内容を決めたら親族間での協議はもちろん、葬儀社のスタッフや葬儀場のスタッフにも忘れずに伝えるようにしましょう。
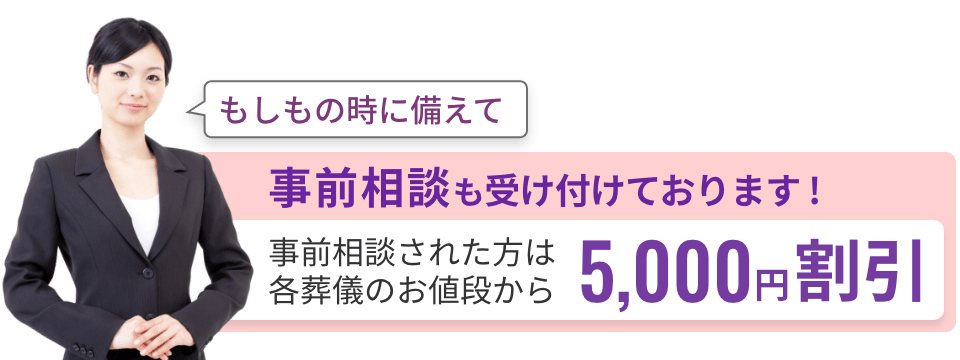
24時間365日 葬儀のご相談可能です!



