喪主の挨拶【挨拶文例】
葬儀では、喪主が故人に代わって参列者の方々に感謝の言葉を伝えることが一般的となっています。
喪主の挨拶は、葬儀の様々な場面で行います。
しかし、そういった機会は滅多にないため、挨拶を任された方は戸惑うこともあるかもしれません。
そこで今回は、喪主の挨拶のタイミングや話すべき内容など、場面ごとに見ていきたいと思います。

目 次
- ■ 喪主挨拶のタイミング
- ■
喪主挨拶のポイント
- ・ 挨拶で意識すること
- ・ 「忌み言葉」に気を付ける
- ・ メモは見てもいいの?
- ■
喪主挨拶基本文例
- ・ 通夜
- ・ 通夜振舞いの開会の挨拶
- ・ 通夜振舞いの閉会の挨拶
- ・ 告別式(出棺時)
- ・ 精進落とし
- ■ まとめ
喪主挨拶のタイミング
通夜
僧侶による読経が終わり、参列者の焼香が終わった後に通夜通夜振舞いの席へと移動します。その前、若しくはお通夜終了後に喪主が挨拶をします。
挨拶は、参列者に対して通夜に参列してくれたことに対するお礼の言葉を伝えます。
また、その際に、翌日以降に予定されている葬儀・告別式の日程や時間についても案内します。
通夜後に行われる通夜振舞いでは、開始時に挨拶をします。
通夜振舞い
通夜後に行われる通夜振舞いでは、開始時に挨拶をします。
告別式(出棺時)
告別式では喪主、若しくは親族の代表者が挨拶をします。
一般的なタイミングは、告別式が終わった後の火葬場へ向けて出棺する前に行います。(告別式中に挨拶を行うケースもあります)
精進落とし
通常、火葬の後には精進落としの食事があります。
ここでの喪主の挨拶は、開始時と終了時に行い、葬儀が無事に終わったことを報告した上で感謝の言葉を伝えます。
喪主挨拶のポイント
挨拶で意識すること
挨拶の内容は以下のことを意識して話します。
- • (自身と)故人との関係性
- • 参列者へのお礼の言葉
- • 故人への生前の厚意に対するお礼
- • 故人のエピソード
- • 残された家族への力添えのお願い
「故人のエピソード」では、以下の内容を盛り込むと、故人が遺族や参列者にとってどのような立場であったのかが明確になります。
- • 故人の社会的な立場の簡単な説明
- • 生前の元気な時の様子
基本的にはある程度決まった文言を使いますが、「故人とのエピソード」については自分なりの言葉で伝えることでより気持ちが伝わります。
「忌み言葉」に気を付ける
葬儀では避けるべき、重ね言葉や不吉なことを連想させる言葉といった「忌み言葉」は使わないようにしましょう。
メモは見てもいいの?
結論から言いますと、メモは見ても問題ありません。
メモを見ずに挨拶しなければいけないと思われる方もいらっしゃいますが、大切なことは参列者の方にしっかりと感謝の気持ちを伝えることです。
そのため、メモを見て話すことは失礼には当たりません。
喪主挨拶基本文例
通夜
本日はお忙しいところ、故人〇〇の通夜にご参列くださいまして、誠にありがとうございます。
生前は、格別のご厚情(こうじょう)を賜りまして、心より感謝申し上げます。
〇〇も皆様に見守られて、喜んでいることかと思います。
なお、明日の葬儀・告別式は〇〇時より△△で執り行う予定でございますので、宜しくお願いいたします。
本日は誠にありがとうございました。
■ 通夜振舞いをご案内する場合
なお、この後、ささやかではございますが、通夜振る舞いをご用意しております。お時間の許す方は、是非、ご一緒に召し上がりながら個人を偲んでやってください。
通夜振舞いの開会の挨拶
本日はお忙しいところ、ご丁寧にお悔やみをくださいましてありがとうございました。
また、生前は、格別のご厚情(こうじょう)を賜りまして、厚く御礼申し上げます。故人〇〇も皆様に見守られまして、喜んでいることかと思います。
なお、明日の葬儀・告別式は〇〇時より△△で執り行う予定でございますので、宜しくお願いいたします。
ささやかではございますが、別室に粗茶など用意しております。どうぞ召し上りながら、故人の思い出話などお聞かせいただければ幸いです。
本日は誠にありがとうございました。
通夜振舞いの閉会の挨拶
本日はお忙しいところ、お越しいただき誠にありがとうございました。
おかげをもちまして、滞り無く通夜を終えさせていただくことができました。
まだごゆっくりしていただきたいところですが、遠方の方もいらっしゃると伺いましたので、この辺で本日はお開きにさせていただきいと思います。
お帰りの皆様は、どうぞお気をつけてお帰りください。
本日は、誠にありがとうございました。
告別式(出棺時)
遺族を代表いたしまして、皆様に一言、ご挨拶申し上げます。
私は故人の長男の〇〇でございます。
本日はお忙しいところ、父〇〇の葬儀にご会葬くださり、誠にありがとうございます。
おかげをもちまして、昨日の通夜、そして本日の告別式を滞りなく執り行うことができました。
故人もさぞかし皆様に感謝していることと存じます。
■ 故人とのエピソードを伝える
父が晩年を豊に過ごすことができましたのも、ひとえに皆様のご厚情のおかげと深く感謝いたしております。
私どもはまだまだ未熟ではありますが、故人の教えを守り、精進していく所存でございます。今後とも、故人同様に、ご指導、ご鞭撻(べんたつ)をいただけますと幸いです。
本日は、誠にありがとうございました。
精進落とし
■ 始まりの挨拶
本日はお忙しいところ、誠にありがとうございました。
お陰さまで滞りなく葬儀を終えることができました。これもひとえに皆様のご厚情のおかげと深く感謝いたしております。
ささやかではございますが、精進落としのお膳をご用意致しましたので、お時間の許す限り、ごゆっくりおくつろぎ下さい。
本日はありがとうございました。
■ お開きの挨拶
本日は、お忙しいところ、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。
皆様に心のこもったお見送りをしていただき、亡き〇〇も喜んでいることと存じます。
まだごゆっくりしていただきたいところですが、皆様お疲れかと思いますので、この辺りでお開きにさせていただきたいと思います。
どうぞみなさま、お気をつけてお帰りください。
本日は誠にありがとうございました。
まとめ
参列してくれたお礼と、故人が生前にお世話になった感謝の気持ちが伝われば十分です。
挨拶は緊張するものではありますが、ゆっくりと自分なりの言葉で伝えましょう。
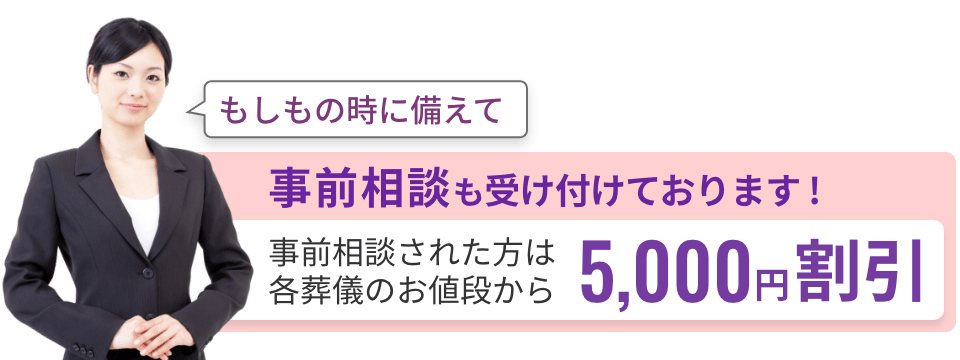
24時間365日 葬儀のご相談可能です!



